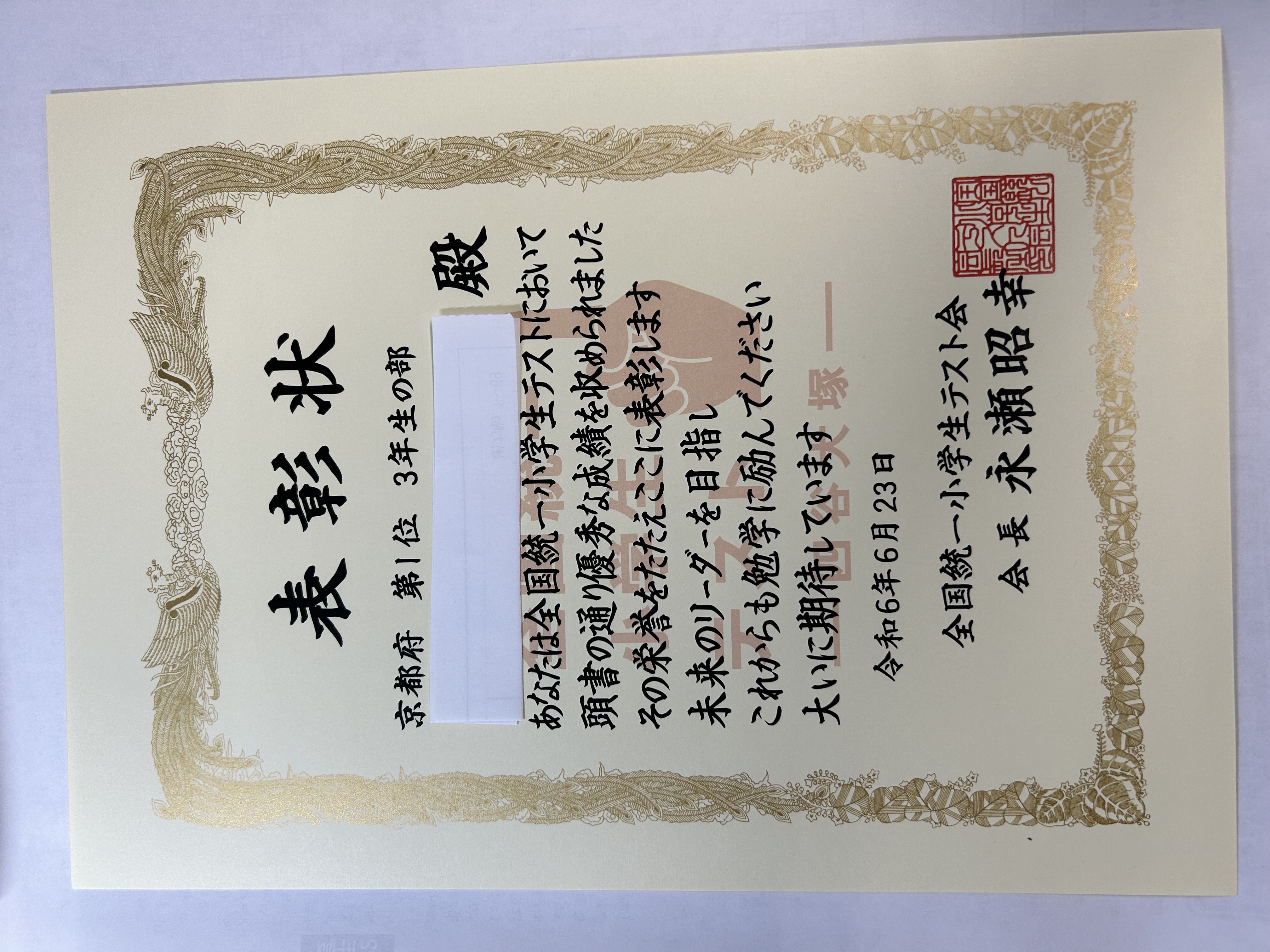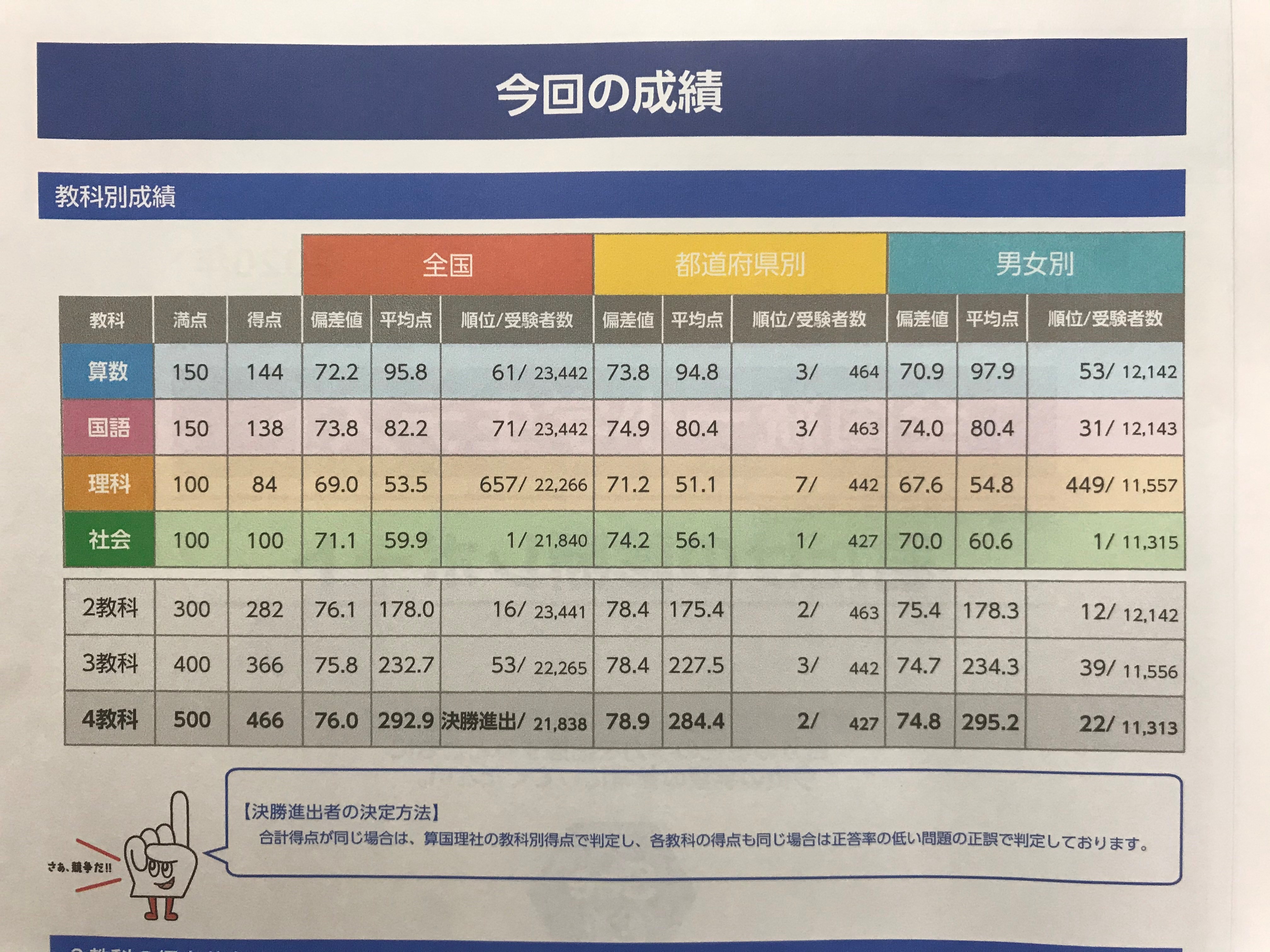学習には、成績をよくするための学習と、頭をよくするための学習があります。
成績をよくするための学習とは、知識を追加する学習です。また、頭をよくするための学習とは、考える力をつける学習ということができます。
しかし、入試に限って言えば、それが中学・高校・大学の入試であっても、○○資格試験であっても、すべて知識の学習でカバーすることができます。
なぜなら、出題範囲が決まっているからです。
範囲が決まっている分野で点数の差をつけるためのテストをしようとすれば、問題はどうしてもパターン化されます。
テストに出される内容は、平凡で大事なことよりも、例外的で点数の差がつきやすいことが主流になっていきます。
これが、現行のテスト中心の学習がもたらす最大の弊害でしょう。
平凡で大事なことであれば、普通に学習していれば、十分身につけていくことができます。
しかし、例外的な事柄の記憶で差のつく学習では、テクニックが必要になります。
そのテクニックとは、現代の入試の分野では、出そうな問題のパターンに慣れていくことです。
だから、逆に言えば、テストに合格するためのいちばん役に立つ学習法は、過去問に多く当たることになります。
小6生で、よく、「過去問は実力がついてからやります」と言う子がいます。
しかし、そうではなく、実力がないうちから慣れるために、過去問に答えを書き込んで読み込んでおくことがいい学習法といえるでしょう。
さて、入試まではこのように過去問中心の成績をよくする学習で間に合わせることができます。
しかし、社会生活には、過去問のない問題が次々と登場します。
過去問も、予備校も、模試もなく、突然目の前に新しい問題が登場するのが現実の社会です。
そのときに成績をよくするための学習しかしてこなかった人は、途方に暮れてしまいます。
考える力のある人は、新しい問題に対しても、自分なりに考えることができるでしょう。
それが、抽象的な思考です。
つまり、問題をそれが問題となっている次元ではなく、一つ上の次元から考えていくことです。
具体的事例の理解には限界があります。
抽象化し 本質を体得していくことで問題解決能力は飛躍的に高まります。
これを通常、私たちは応用力や生きる力などと呼び、その必要性を説いています。
仏陀は、ある村で、子供を亡くした母親から、「子供を生き返らせてほしい」と頼まれます。仏陀にはそのことは可能でしょう。しかし、子供を生き返らせたところで、問題は根本的に解決するわけではありません。世界中の子供を生き返らせ続ける展望がなければ、解決は場当たり的なものにならざるを得ないのです。そこで、仏陀は、「これまで一度も死んだ人を出したことのない家からケシの種を三粒もらってきなさい」と言います。ここに、「生き返らせる」「生き返らせない」という次元を超えた、当時可能だった最善の解決策があると思います。
第一次南極観測隊の西堀栄三郎は、南極に着き、いざ基地を建築する段になって、日本から釘を持ってきていなかったことに気がつきます。「基地を作ることを諦めるか」「日本まで釘を取りに帰るか」などという次元の選択肢を超えて、西堀氏は、並べた板に水をかけ、凍った水で基地を建設するというやり方を提案します。
いずれも、具体的な低い次元では解決できなかったことが、抽象的な次元で解決をみています。
抽象的な考えとは、「人間とはそもそも……」「釘とはそもそも……」という考え方です。
この「○○とはそもそも……」と考えるためには、「○○とは」という抽象的にものごとを考える力が必要です。
では、単に成績をよくするための学習ではなく、地頭をよくする学習とはどのようにしたらいいのでしょう。
1を10回加えるときに、1+1+1+……と考える方法と、1×10と考える方法があります。
問題のレベルが低いときは、掛け算で考えるよりも、1+1+1+……と力技で計算して答えを出す方が早いことがあります。
そして、日常生活のほとんどの場面は、この力技で処理していくことができます。
例えば、ある人数をいくつかのグループに分ける必要があった場合、人数が少なければ、だれかが数えて分けてしまうのがいちばん簡単なやり方です。
10人を3つのグループに分けるときは、3人ずつ分けていき余った1人はどこかのグループに適当に入れれば済みます。
しかし、百人を3つに分けるときに、これと同じ方法が取れるでしょうか。千人ではどうでしょうか。
人数が多くなったときにグループ分けする方法は、もっとスマートに考える必要があります。
それは、「それでは、1万人のみなさん。みなさんの誕生日を3で割って、余りが1の人はAグループ、余りが2の人はBグループ、余りが0の人はCグループに行ってください」というような方法です。
こういう方法であれば、3万9千人の人を7つのグループに分けるなどという面倒なこともすぐにできます。
しかし、日常生活では、そういう大人数を分ける必要が出てくることはまれです。
抽象的に考えるタイプの人よりも、単純に大声を出して行動力を発揮できるタイプの人の方が活躍することが多いのです。
ところが、人間は成長するにつれて、だんだん難しい役割を担うようになります。
課題が難しくなり守備範囲が広くなるにつれて、単に行動力があるだけの人よりも、思考力のある人の方が仕事ができるようになってきます。
このように考えると、頭をよくするとは、抽象的な力を高めることだということがわかります。
掛け算は、足し算よりも抽象的思考を必要とするため、扱う数が多くなるにつれて便利になってきます。
人生も似ています。その人の生活範囲が狭くて単純なときは、行動力がいちばんです。
しかし、複雑さが増すにつれて、抽象的に考える能力が必要になっていきます。
抽象的に考える能力とは、現象の背後にある本質を考える能力です。
以前、高校生の化学の宿題を見たことがあります。
どのページもほとんど計算問題です。
確かにこういう練習問題を多数やれば、計算には慣れるだろうとは思いましたが、あまり知的な学習とは思えませんでした。
やればできる問題に取り組むのは、時間の無駄です。
もし、私が先生の立場であれば、次のように宿題を出すでしょう。
「この問題集を解答・解説を見ながら読んで、解答が理解できなかった問題だけを書き出してくること。」
できる問題を作業的にやるのではなく、できない問題を自覚することこそが真の学習だからです。
ところが、生徒も先生も保護者の方も、多くの場合、できる問題を解いている姿を学習している姿と思いがちです。
しかし、できなかった問題にも二種類あります。
単に記憶していないためにできなかった問題は、本当の意味でできなかった問題ではあり、解答を見ればすぐにわかるような問題がこういう問題です。
そうではなく、本当にできない問題とは、その問題の背後にある本質がまだ理解できていない問題のことです。
このような問題ができるようになったとき、人間の抽象能力が一つ前進したと言えるのです。
このことは、化学や数学のような問題に限りません。
むしろ、学校の学習では評価される機会があまりない分野にこそ、このような抽象化能力が必要とされてくるのです。
抽象化能力を高める有効な方法の一つに読書があります。読書は、言語によって物事を抽象化します。
しかし、先に挙げた冬休みの計算の宿題のように、抽象化能力をあまり高めない読書もあります。
それはどういうものかというと、現象こそ多様に見えますがその背後にある本質にあまり変化がない読書です。
これは計算練習と同じで、見た目には次々と新しい問題を解いているように見えますが、やっていることの本質はもうすっかりわかっているというタイプの読書です。
読書の目指す方向は、抽象度の高い読書、つまり難しい本を読むことにあります。
また、自分が既に知っている分野だけでなく、未知の分野に読むジャンルを広げていくことが、発展的な読書の方向性です。
しかし、人間には成長に応じた発達段階があります。小学生のころから、難しい本や未知の分野の本を読ませようとすると、かえって読書量が確保できなくなり、マイナス面が大きくなります。
小中学生のころは、楽しい本や感動できる本を中心に多読をするということが重要です。
多読によって、そののち広がる読書の発展に寄与する言語能力の基礎ができていきます。
しかし、単なる多読でなく、難読を志向した多読、つまり、自分の興味の持てる分野で説明文や意見文につながる読書をしていくことが小中学生の読書の課題となります。
高校生や大学生のころは、難しい本を読める時期です。
このころになると、難しいことそのものに挑戦したいという知的好奇心が旺盛になってきます。
この時期に、歯が立たないような本に挑戦することで本当の読書力がついていきます。
しかし、これもただ難読をするだけでなく、その後の新分野にジョイントするような未知のジャンルに広がる難読をしていくことが大切です。
多読→難読は、人間の抽象化能力の形成の第一歩です。
夏休みもアト少し。
この思う存分本を読む時間が取れる期間を大切にして、あなたなりの読書のかたちを進めてほしいものです。